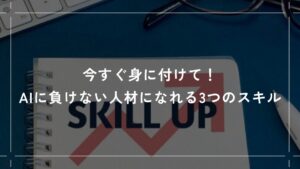「今年こそ家計簿を続けよう!」と意気込んでみたものの、気づけば三日坊主…そんな経験はありませんか?
家計簿は、頑張りたい気持ちとは裏腹に、なかなか続かないものですよね。でも、それは決してあなたがズボラだからではありません。もしかしたら、やり方が自分に合っていなかっただけかもしれません。
この記事では、「家計簿が続かない…」と悩むあなたに向けて、家計管理を楽しく続けるためのヒントをお伝えします。無理なく続けられる家計簿のコツから、もしものときのプロに頼る方法まで、一緒に見ていきましょう。
家計簿が続かない理由とは?

※イメージ画像
挫折する主な原因を知ろう
家計簿が続かない原因は、人それぞれ。でも、多くの人が共通して抱える原因がいくつかあります。
- 完璧主義になってしまう: 1円単位まできっちりつけようとしたり、毎日欠かさず記録することにこだわったり。完璧を求めすぎると、少しでもズレたときに「もうダメだ…」と諦めてしまいがちです。
- 支出を把握しきれない: レシートを溜め込んでしまい、何に使ったか思い出せない。いざ家計簿をつけようと思っても、手間がかかりすぎてやる気がなくなってしまいます。
- 目的が曖昧: 「なんとなく貯金したい」という漠然とした目標では、モチベーションを保つのが難しいです。家計簿をつけることで、具体的にどうなりたいのかが明確でないと、ただの面倒な作業になってしまいます。
無理なく続けるための考え方
家計簿を続けるためには、まず考え方を変えることが大切です。完璧を目指すのではなく、**「ざっくりでもOK」「ゆるく続ける」**ことを目標にしてみましょう。
家計簿の目的は、家計全体をざっくり把握することです。毎日すべての出費を細かく記録しなくても、大きな流れさえつかめれば十分。たとえば、1週間に1回、まとめてレシートを整理するだけでも家計簿はつけられます。
また、家計簿をつけることで、将来の楽しみのためにどれだけお金を貯められるか、具体的な数字が見えてきます。たとえば、「この夏に家族旅行に行きたい」「老後に趣味を楽しむためのお金が欲しい」といった具体的な目的を持つことで、家計簿がただの作業から「未来の自分への投資」に変わります。
主婦にありがちな失敗例
主婦の家計簿にありがちな失敗例をいくつかご紹介します。
- 子どもの出費を細かく分類しすぎる: 「おやつ代」「文房具代」「習い事代」など、子どもの出費を細かく分けすぎると、記録が複雑になりがちです。すべてを「子ども費」とひとまとめにするなど、シンプルに考えてみましょう。
- スーパーでの買い物を一括計上: スーパーでの買い物を「食費」とだけ記録していませんか? 実は、日用品や衣類など、食費以外のものも含まれていることがあります。大まかに分けるだけでも、支出の内訳が見えやすくなります。
- 家族の協力を得られない: 一人で頑張りすぎていませんか? 家計簿は家族みんなで取り組むものです。夫や子どもにも家計の状況を共有し、協力してもらうことで、家計管理がもっとスムーズになります。
自分に合った家計簿の選び方

※イメージ画像
手書き・アプリ・エクセルの比較
家計簿には、主に手書き、アプリ、エクセルの3つの方法があります。それぞれの特徴を理解し、自分に合った方法を選びましょう。
| 種類 | メリット | デメリット | こんな人におすすめ |
| 手書き | ・書くことで支出を意識しやすい ・自分好みのデザインにできる ・特別な知識や道具が不要 | ・集計が面倒 ・記入の手間がかかる ・持ち運びが不便 | ・書くことが好き ・お金と向き合う時間を大切にしたい ・細かい作業が苦手ではない |
| アプリ | ・スマホでいつでもどこでも記録できる ・自動でグラフ化してくれる ・銀行口座やクレジットカードと連携できる | ・セキュリティが気になる ・連携機能がうまく使えないこともある ・慣れるまで操作が難しい場合も | ・隙間時間にサッと記録したい ・自動で集計してほしい ・スマホやIT機器の操作に慣れている |
| エクセル | ・自分好みにカスタマイズできる ・関数を使えば自動で計算できる ・パソコンで管理したい | ・初期設定に手間がかかる ・ある程度のPCスキルが必要 ・スマホでの入力はしづらい | ・PC作業が得意 ・独自のフォーマットで管理したい ・家計簿をデータとして残したい |
家計簿アプリのおすすめ3選
ここでは、多くの人に愛用されている家計簿アプリを3つご紹介します。
- マネーフォワード ME: 銀行やクレジットカードと連携し、自動で家計簿を作成してくれる便利なアプリです。レシートを撮影するだけで読み取ってくれる機能もあり、手入力を減らしたい人におすすめです。
- Zaim: シンプルで使いやすいデザインが特徴。入力が簡単なので、家計簿初心者でも挫折しにくいです。予算管理や、家計診断機能も充実しています。
- Osidori: 夫婦や家族で家計簿を共有したい人におすすめのアプリです。それぞれの収入・支出を一緒に管理できるので、家計の透明性が高まります。
主婦に人気の家計管理法
最近は、家計簿にこだわらず、もっと自由に家計を管理する人も増えています。たとえば、こんな方法があります。
- 袋分け管理: 1週間や1ヶ月の予算を食費や日用品など項目別に袋に分けて管理する方法です。現金で管理するので、お金の使いすぎを防げます。
- クレジットカードやキャッシュレス決済の一本化: 複数のクレジットカードや電子マネーを使うと支出の管理が複雑になります。メインで使うものを1〜2つに絞るだけで、支出の把握がグッと楽になります。
家計簿を習慣化する5つのコツ

※イメージ画像
毎日の記録を簡単にする工夫
家計簿を続けるには、いかに記録を楽にするかがポイントです。
- レシートはその場で撮影: 買い物をしたら、すぐにレシートを撮影して家計簿アプリに入力しましょう。家に帰ってからだと、何を買ったか忘れてしまったり、レシートをなくしてしまったりすることがあります。
- スマホのメモ機能を活用: レシートがもらえない場合や、現金で支払った場合は、スマホのメモ機能にサッと記録しておきましょう。「カフェ代 1,000円」など、簡単にメモするだけでOKです。
無理のない記録タイミングとは?
毎日つけるのが難しいと感じるなら、記録するタイミングを決めてみましょう。
- 週末にまとめて: 1週間のレシートやメモをまとめて家計簿に入力します。
- 月末にまとめて: 1ヶ月分の支出を一気に振り返ります。
- 給料日に: お給料が入った日に1ヶ月の予算を立て、前月の支出を振り返ります。
記録をサボった日の対処法
「今日は疲れたから明日でいっか…」と記録をサボってしまった日があっても大丈夫。家計簿が続かない原因は、この「サボり癖」がついてしまうこと。でも、一度サボってしまっても、そこで諦めないことが大切です。
「1日だけサボっちゃったけど、また明日から頑張ろう!」と、ポジティブに捉えましょう。完璧主義を捨てて、ゆるく続けることを目標にすることで、家計簿は長く続けられるようになります。
項目別に支出を整理する方法
項目設定の基本とポイント
家計簿の項目は、細かすぎてもざっくりしすぎてもダメ。家計全体を把握しやすくするために、適切な項目設定をすることが大切です。
- 基本の項目: 食費、日用品、通信費、水道光熱費、家賃(住宅ローン)、保険料、被服費、医療費、交通費、娯楽・交際費、雑費、教育費など
- オリジナルの項目もOK: 自分のライフスタイルに合わせて項目をアレンジしましょう。たとえば、「子ども関連費」や「美容代」など、自分にとって見直したい項目を設けるのもおすすめです。
固定費・変動費の分け方
支出は大きく固定費と変動費に分けることができます。
- 固定費: 毎月決まった額を支払う費用。家賃、住宅ローン、保険料、通信費など。
- 変動費: 毎月支払う額が変わる費用。食費、日用品、被服費、娯楽・交際費など。
この2つに分けることで、家計の何にお金を使っているのかが明確になり、節約できる項目が見つけやすくなります。
費目を見直すタイミング
家計簿をつけていると、意外なところで無駄な出費があることに気づくことがあります。
- 定期的に項目を見直す: 半年や1年に一度、費目を見直してみましょう。たとえば、「趣味に使っている費用」が毎月かなりの額になっていることに気づけば、趣味の費用を少し見直すきっかけになります。
- ライフスタイルの変化: 子どもが学校に入学したり、家族の人数が変わったり、ライフスタイルに変化があったときも項目を見直す良いタイミングです。
家計簿を貯金につなげる方法
支出を見直すチェックポイント
家計簿は、ただ記録するだけでは意味がありません。家計簿を「貯金」という成果につなげるためには、支出を見直すことが大切です。
- 「何に使ったか」を把握する: まずは、何にどれくらい使っているのかを把握しましょう。特に、変動費は日々の意識で節約できる部分が多いです。
- 「無駄な出費」を見つける: 「なんとなく買ったもの」「必要ないのに契約しているサブスクリプション」など、無駄な出費がないかを探してみましょう。
目標設定でモチベーションUP
「なんとなく貯金したい」ではなく、「何のために貯金するのか」を明確にすることで、モチベーションが維持しやすくなります。
- 短期目標: 「3ヶ月で5万円貯める」
- 中期目標: 「1年で家族旅行に行くための資金を貯める」
- 長期目標: 「老後の生活資金を確保する」
目標を立てて、達成できたら自分にご褒美をあげるなど、楽しみながら取り組んでみましょう。
節約と我慢のバランスのとり方
節約と聞くと、「我慢ばかり…」とネガティブなイメージを持つ人もいるかもしれません。しかし、無理な我慢は長続きしません。
- メリハリをつける: 節約する部分と、お金をかける部分にメリハリをつけましょう。「食費は抑えるけど、家族で食事に行くときは好きなものを食べる」など、自分にとって大切なものにはお金をかけてもOKです。
- 「我慢する節約」から「賢く使う節約」へ: 家計簿をつけることで、お金の使い方を意識できるようになります。「この買い物は本当に必要?」と立ち止まって考える習慣をつけることで、自然と無駄な出費が減っていきます。
家計のプロに相談するという選択肢

※イメージ画像
相談サービスを使うメリットとは
「家計簿をつけているけど、このままで本当に大丈夫?」 「自分の貯金方法が合っているのか不安…」
もしそう感じているなら、家計のプロに相談してみるのも一つの選択肢です。
- 客観的なアドバイスをもらえる: 自分では気づけないお金の使い方や、家計の問題点を客観的に指摘してもらえます。
- 専門知識を学べる: 家計管理や資産形成に関する専門的な知識を、わかりやすく教えてもらえます。
- 具体的な解決策を提案してもらえる: あなたのライフスタイルや目標に合わせて、最適な家計改善プランを一緒に考えてくれます。
「マネドア」で相談できる内容
「マネドア」は、家計の悩みを無料で相談できるサービスです。家計簿のつけ方から、貯金や投資の方法まで、幅広い内容を相談できます。
- 家計簿が続かない、つけ方がわからない
- 貯金がなかなか増えない
- 将来の教育資金や老後資金が不安
- 住宅ローンの見直しをしたい
など、どんな小さな悩みでもOK。安心して相談できます。
無料でプロに相談する方法
家計簿をつけるだけでは不安が残る…という方は、専門家に相談してみませんか?
「マネドア」なら、家計のプロに無料で悩みを相談できます。
▶︎ マネドアの無料相談はこちら
まとめ
この記事では、家計簿が続かない理由から、自分に合った方法、そして家計を改善するための具体的なコツまでをお伝えしました。
家計簿は、完璧でなくても大丈夫。「ゆるく、楽しく、自分らしく」続けることが大切です。
もし、一人で家計管理を続けることに不安を感じたり、「もっと具体的なアドバイスが欲しい」と思ったら、いつでもプロに相談できるサービスがあることを覚えておいてください。